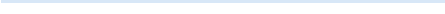■ ham-R "Stay Hungry Stay Foolish" :download
■ ham-R "Seven Demos" :download
■ ham-R "Milestones" :download
■ ham-R × Y.G.S.P "Future Vintage" :download
THA BLUE HERBの"STILLING,STILL DREAMING"、MSCの"MATADOR"、SEEDAの"花と雨"、あるいはキングギドラの"空からの力"でもなんでもいい。ほとんど無名だったなか多くのリスナーから支持されて、歴史に名前を残した作品を見ていると、その特徴は「自分の表現に確固たる自信を持っている」ことと、「それまでには無い新しいアプローチで表現している」こと、更に「自分を取り巻く環境や時代の流れを的確に捉えている」というところにあることに気づく。つまり、リスナーにとって刺激的で新鮮に聴ける作品とは日本語ラップというジャンルの中心からではなく、それまでのシーンの流れから外れたカッティングエッジから産まれ、そういったフレッシュな表現を次々と取り込んでシーンは成熟していくということだ。
もちろん、ひとときカッティングエッジにあった表現もシーンに取り込まれていくことで、どんどん古びたありきたりの表現になっていく。だけども、いつの時代であっても「自分の表現に確固たる自信を持」ち、「それまでには無い新しいアプローチで表現」をし、「自分を取り巻く環境や時代の流れを的確に捉え」ることのできたアーティストがシーンに恵みを与え、バリエーションを豊かにすることは疑いようもない。
SEEDA、ANARCHY、SIMON、NORIKIYO、般若、TWIGY、KREVA、RHYMESTER、鬼、S.L.A.C.K.、RAU DEF、志人、ICE DYNASTY、ROMANCREW、サイプレス上野とロベルト吉野……こうやって今年アルバムやEPを発表したアーティストの名前を並べると、まだ2ヶ月残しながら2011年は日本語ラップにとって本当に豊作の年だった。それぞれのラッパーの持つカラーがアルバムにきちんと反映されていて、音楽的なクオリティの部分のみでいえば期待はずれとなったものはあまり無かったのではないかと思う。
しかしシーンにとって刺激となり、これまでの表現を変えるほどの力を持った作品は「無かった」と、バーチャルアイドルラッパーRANLのミックステープ(Service Time)がネットで一部集中的に話題を呼んでいたことを踏まえて裏から見れば、そう言い切ってしまってもいいのではないか。"リアル"を追求してきた日本語ラップへの皮肉かのようにまったく実体がなく、確かなラップスキルと日本語ラップの知識を楯に半ば自虐的に日本語ラップシーンそのものをアニメ声で揶揄していくこのラッパーが持つ面白さは、日本語ラップのカッティングエッジから産まれていることをこの際強調しておきたい。何にせよ、まるで日本語ラップの文脈を逆流していくようなRANLの"Service Time"が新鮮に聴こえてしまった身からすると、これから先の日本語ラップというジャンルそのもの自体に一抹の不安を感じてしまう。この音楽にはまだカッティングエッジに立てるアーティストが出てくるのだろうか?
1年ほど前になるけども、立て続けにミックステープをリリースしていたアーティストがいた。いま彼がリリースした作品群"Stay Hungry Stay Foolish"、"Seven Demos"、"Milestones"、"Future Vintage"から感じ取れるのは、まさしく「自分の表現に確固たる自信を持」ち、「それまでには無い新しいアプローチで表現」し、「自分を取り巻く環境や時代の流れを的確に捉え」る姿勢だった。
たとえば、1stミックステープ(Stay Hungry Stay Foolish)に収録されている"Japanese Average Line"や"R-25"といった曲で描かれる現代の若者の視線には社会に出ている人間なら誰でも理解できるウィットに富んだ面白さがあるが、それだけでなく、その目線の先が日本の社会システムあるいは音楽業界の崩壊にまでうつっていったときに、とてもコンシャスな説得力を帯びていくことに気づく。音楽業界や、日本という国だけでなく、アメリカを代表するエネルギー社会全体が沈んでいこうとしている"いまの状況"を捉え、そのなかでサバイブしていく使命を背負わされた若者の視線は、そんな終わっている状況を作り上げた上の世代を痛烈に批判する姿勢にも繋がっていく。ZEEBRAとRAU DEFのビーフでも ham-Rがその裏からビーフを演出していたフシがあったけども「自分の表現に確固たる自信を持」って、古いシステムや考え方をぶち壊して新しい世界をつくっていこうとする姿勢は、そんな "状況分析"のもとでつくられているように見えてくるのだ。いまの"終わっている状況"を作り出した古いシステムとその遺産を押し付けられる若い世代が、新しいシステムの波に乗って、そいつらをぶっ壊していくことを宣言する姿勢には充分すぎるほどの説得力がある。
"まずはぶっ壊す腐った地球ってとこの日本って国のしょうもない音楽。ここ東京から最新ってやつを教えてやらぁ"(Knock Knock)
"いつまで経ったらお前の言うブリンブリンを若いやつらがゲットできるの?はたから見たらやたら陰気くさいしみっともない感じ。ほらオマエだよオマエ。うすうす感じ取っているんだろ?Hi!追い出される前に消えな。じゃなきゃそろそろ血祭りにあげんぞオーライ?"(Hi!)
古いシステムや考え方を全て破壊してやるという圧倒的な自信、的確な状況分析と視野の広さ、そして何よりもそれらを裏打ちする優れた音楽的センス、それらは全てカッティングエッジに立つことを可能にするエッセンスだ。ham-Rが一連のミックステープで示した上の世代や古いシステムに対してみせる攻撃的な一面は、キングギドラ、THA BLUE HERB、MSCの処女作ではまた別の形で露出していた。いまインターネットから、JPRAP.COMを媒体としてこれまでとは異なる才能を持ったアーティストが次々と出てきているけども、もし彼らがham-Rと同じような姿勢と覚悟を持ってカッティングエッジに立つことが出来るのであれば、きっと日本のヒップホップにとって大きな力の源になるだろう。
"When I was young, there was an amazing publication called The Whole Earth Catalog, which was one of the bibles of my generation. It was created by a fellow named Stewart Brand not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 1960's, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form, 35 years before Google came along: it was idealistic, and overflowing with neat tools and great notions.
Stewart and his team put out several issues of The Whole Earth Catalog, and then when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words: "Stay Hungry. Stay Foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay Hungry. Stay Foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you.
Stay Hungry. Stay Foolish."(Stay Hungry Stay Foolish)